新海誠監督の話題作「すずめの戸締まり」には、印象的なフレーズがいくつか登場します。
その中でも特に耳に残るのが、閉じ師である宗像草太が扉を閉める際に唱える「お返し申す」という言葉です。
一見シンプルな言葉ですが、物語の中で繰り返し使われることで、観客に強い印象を与えます。
この記事では、この「お返し申す」というフレーズの意味や背景、作品に込められた重要な役割について詳しく考察していきます。
「お返し申す」とは?基本的な意味を解説
「お返し申す」というフレーズは、作中で扉を閉める儀式の際に唱えられる祝詞(のりと)の一部として登場します。
この言葉には日本古来の宗教的な意味合いが込められており、単なる呪文やおまじないではありません。
祝詞としての「お返し申す」の役割
祝詞とは、神道において神様に祈りや感謝、願い事を伝えるための言霊(ことだま)です。
日本では古来より、言葉には霊的な力が宿るとされ、正しい言葉を正しい形で発することが重要と考えられてきました。
作中で草太が扉を閉める際に唱える「お返し申す」は、災いの力や常世の存在を元の場所へと「お返し」するための言葉です。
これは、単に扉を物理的に閉める行為ではなく、精神的な封印の儀式でもあります。
日本神話や伝統文化との関連性
「お返し申す」という表現は、神道や日本の民間信仰に深く根ざしています。
特に、神話や古事記において、災厄や死、穢れ(けがれ)を「元の世界」に送り返す儀式が数多く登場します。
例えば、禊(みそぎ)や祓いの儀式は、不要な穢れを自然の中に「お返し」する行為です。
草太が唱えるこの祝詞も、そうした伝統的な儀式の延長線上にあると考えられます。
なぜ「すずめの戸締まり」で重要なフレーズなのか?
「すずめの戸締まり」で繰り返し登場する「お返し申す」という言葉は、単なる儀式の一部ではなく、物語全体のテーマと深く結びついています。
このフレーズがなぜ重要な役割を果たすのか、その背景にある意味を探ってみましょう。
扉を閉める儀式的な意味合い
作中で描かれる「後ろ戸」は、常世(死者の世界)と現世(生者の世界)をつなぐ境界です。
この扉が開いてしまうと、ミミズと呼ばれる災厄が現世にあふれ出し、地震や自然災害を引き起こします。
草太が扉を閉める際に唱える「お返し申す」は、この災いの力を再び元の場所へと送り返すための重要な儀式です。
この行為は、単に物理的な扉を閉めるだけでなく、世界の秩序を保つための精神的な儀式としての意味を持っています。
キャラクターの心の成長とリンクする場面
「お返し申す」という言葉は、主人公・すずめの心の成長とも深く関わっています。
物語の序盤では、扉を閉める役割は主に草太が担っていましたが、旅を続ける中ですずめ自身もこの儀式を学び、やがて自分の意志で「お返し申す」と唱えるようになります。
この瞬間、すずめは過去の喪失や悲しみと向き合う勇気を手に入れ、自らの成長を象徴する存在へと変化します。
つまり、「お返し申す」は、単なる儀式の言葉ではなく、すずめの内面的な成長と物語の核心を象徴する言葉なのです。
「すずめが自ら『お返し申す』と唱えるシーンは、彼女が過去の自分を乗り越える瞬間だった。感動した!」(視聴者の感想より)
視聴者が考える「お返し申す」の解釈
このフレーズについて、観客はさまざまな解釈をしています。
ここでは、ネット上で語られている考察や意見を紹介しながら、その意味をさらに掘り下げていきます。
ネット上の考察と解釈まとめ
多くの視聴者が指摘するのは、「お返し申す」という言葉が持つ二重の意味です。
一つは、物語上の儀式的な意味であり、もう一つは人間の感情の整理という側面です。
- 「災いを封じ込めるだけでなく、自分の心の中の悲しみや未練を“お返し”する意味もある気がする。」
- 「『お返し申す』は、過去の出来事に対する感謝や別れの言葉としても解釈できる。」
このように、一つの言葉に多層的な意味が込められていることが、観客の心に深く残る理由の一つです。
「お返し」の概念が示すメッセージ性
「お返し申す」に込められているのは、単なる封印や祓いの意味だけではありません。
むしろ、「感謝」や「別れ」という、人間関係における重要な感情が象徴されていると考えられます。
過去の出来事や失ったものに対して、ただ「忘れる」のではなく、心の中で整理し、感謝を込めて送り出すという行為。
これが「お返し申す」という言葉に込められた、深いメッセージなのです。
「過去は消せないけど、心の中で整理して“お返し”することで前に進める。それがこの言葉の力だと思う。」(SNSの考察より)
ここまでが第2回目の内容です。
次回(第3回目)では、「新海誠監督が込めた意味とは?」から記事
なぜ「すずめの戸締まり」で重要なフレーズなのか?
「すずめの戸締まり」で繰り返し登場する「お返し申す」という言葉は、単なる儀式の一部ではなく、物語全体のテーマと深く結びついています。
このフレーズがなぜ重要な役割を果たすのか、その背景にある意味を探ってみましょう。
扉を閉める儀式的な意味合い
作中で描かれる「後ろ戸」は、常世(死者の世界)と現世(生者の世界)をつなぐ境界です。
この扉が開いてしまうと、ミミズと呼ばれる災厄が現世にあふれ出し、地震や自然災害を引き起こします。
草太が扉を閉める際に唱える「お返し申す」は、この災いの力を再び元の場所へと送り返すための重要な儀式です。
この行為は、単に物理的な扉を閉めるだけでなく、世界の秩序を保つための精神的な儀式としての意味を持っています。
キャラクターの心の成長とリンクする場面
「お返し申す」という言葉は、主人公・すずめの心の成長とも深く関わっています。
物語の序盤では、扉を閉める役割は主に草太が担っていましたが、旅を続ける中ですずめ自身もこの儀式を学び、やがて自分の意志で「お返し申す」と唱えるようになります。
この瞬間、すずめは過去の喪失や悲しみと向き合う勇気を手に入れ、自らの成長を象徴する存在へと変化します。
つまり、「お返し申す」は、単なる儀式の言葉ではなく、すずめの内面的な成長と物語の核心を象徴する言葉なのです。
「すずめが自ら『お返し申す』と唱えるシーンは、彼女が過去の自分を乗り越える瞬間だった。感動した!」(視聴者の感想より)
視聴者が考える「お返し申す」の解釈
このフレーズについて、観客はさまざまな解釈をしています。
ここでは、ネット上で語られている考察や意見を紹介しながら、その意味をさらに掘り下げていきます。
ネット上の考察と解釈まとめ
多くの視聴者が指摘するのは、「お返し申す」という言葉が持つ二重の意味です。
一つは、物語上の儀式的な意味であり、もう一つは人間の感情の整理という側面です。
- 「災いを封じ込めるだけでなく、自分の心の中の悲しみや未練を“お返し”する意味もある気がする。」
- 「『お返し申す』は、過去の出来事に対する感謝や別れの言葉としても解釈できる。」
このように、一つの言葉に多層的な意味が込められていることが、観客の心に深く残る理由の一つです。
「お返し」の概念が示すメッセージ性
「お返し申す」に込められているのは、単なる封印や祓いの意味だけではありません。
むしろ、「感謝」や「別れ」という、人間関係における重要な感情が象徴されていると考えられます。
過去の出来事や失ったものに対して、ただ「忘れる」のではなく、心の中で整理し、感謝を込めて送り出すという行為。
これが「お返し申す」という言葉に込められた、深いメッセージなのです。
新海誠監督が込めた意味とは?
「すずめの戸締まり」における「お返し申す」という言葉は、新海誠監督が本作で伝えたかった深いメッセージと密接に結びついています。
単なる儀式の呪文ではなく、人生における大切なテーマがこの一言に込められているのです。
災害と記憶、再生への祈りとしての役割
本作は、東日本大震災をはじめとする多くの自然災害を背景に描かれています。
新海誠監督はインタビューの中で、災害と向き合うことがいかに困難であるか、そしてその記憶を風化させないことの重要性について語っています。
「お返し申す」という言葉は、災厄を封じ込める祈りであると同時に、過去の悲しみや喪失を受け入れ、再生へと歩み出すための儀式でもあるのです。
これは、単なるフィクションの中だけの話ではなく、現実世界の私たちに向けたメッセージとも言えるでしょう。
「災害や悲しい出来事を忘れるのではなく、それと向き合い、心の中で整理していくこと。それが“お返し申す”の本当の意味だと思う。」(ファンの考察より)
人と自然の関係性を示す深いメッセージ
「すずめの戸締まり」は、自然災害というテーマを通して人と自然のつながりについても描いています。
自然は時に私たちに恵みを与え、時に災厄という形で試練を与える存在です。
「お返し申す」という言葉には、自然の力に対する畏敬の念と、そのバランスを保つための祈りが込められています。
私たちは自然を完全にコントロールすることはできませんが、共存するための知恵と心構えを持つことができるはずです。
まとめ:「お返し申す」に込められた想いとは
「すずめの戸締まり」に登場する「お返し申す」というフレーズは、単なる儀式の一部ではなく、物語の核心をなす重要な言葉です。
この言葉には、次のような深い意味が込められています。
- 災厄を元の場所に送り返す祈り
- 過去の悲しみや喪失と向き合うための言葉
- 自然への畏敬と共存のメッセージ
- 個人の成長と再生への一歩
新海誠監督は、このシンプルなフレーズに多層的な意味を込め、私たちに「忘れてはいけないもの」と向き合うきっかけを与えてくれました。
「お返し申す」という言葉を改めて噛みしめることで、作品の見方が変わり、新たな感動が生まれるかもしれません。
あなたは、この言葉にどんな意味を感じましたか?
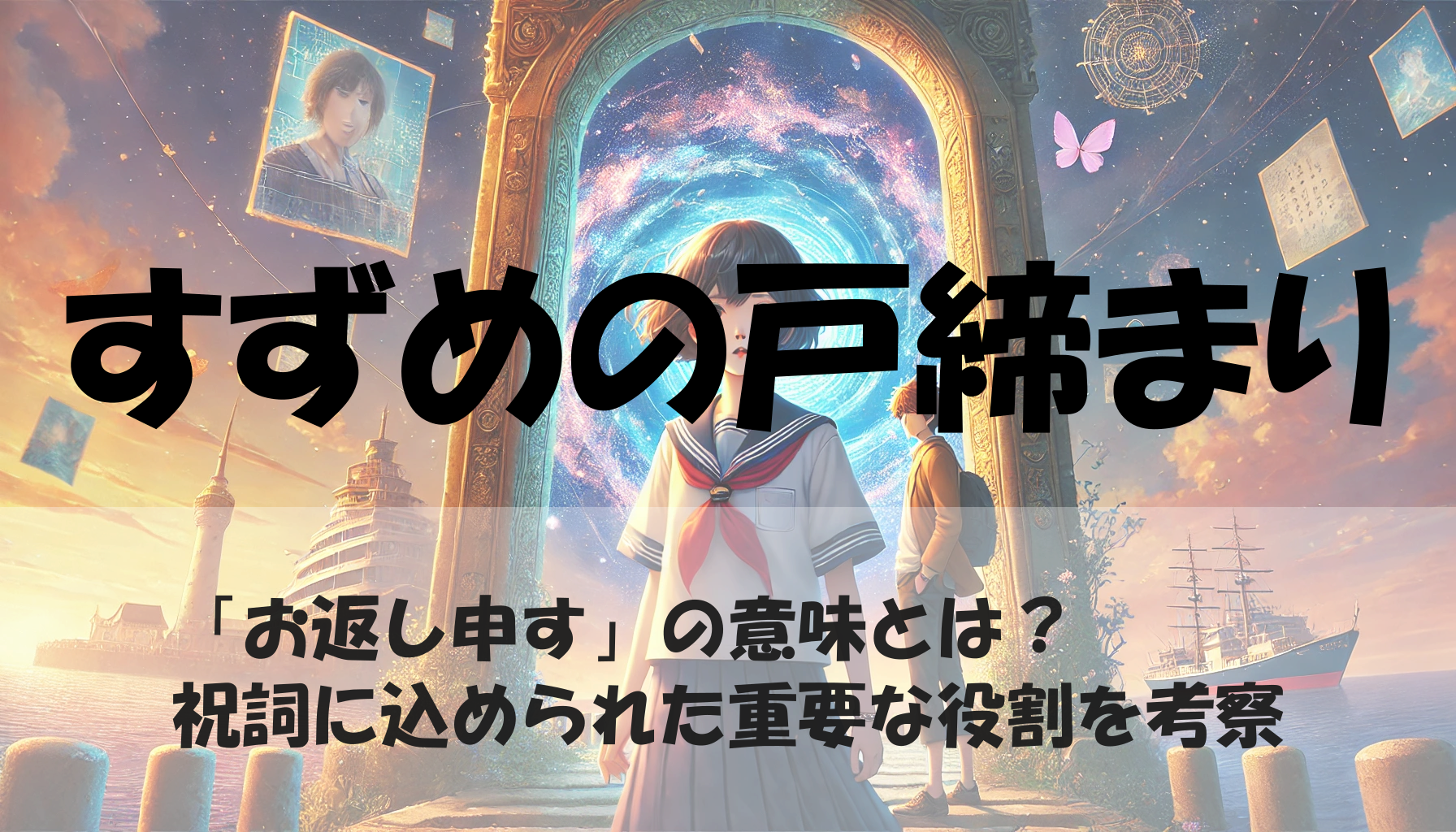
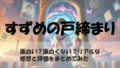
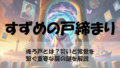
コメント